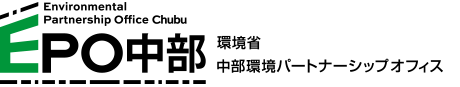EPO NEWSEPO中部のお知らせ
中部ブロック地域循環共生圏づくり中間共有会2025を開催しました
2025.11.21
地域循環共生圏づくり支援体制構築事業の選定団体が集まり、取組状況を報告し合う『中間共有会』の中部ブロック会合を、11月13日-14日に愛知県半田市で開催しました。
会合には、中部の3地域6団体が集合し、取組内容や課題感を相互参照しつつ、それぞれの活動の意義をどのように感じているか共有するディスカッションなどを行いました。
参加団体(中部の3地域6団体)
| 活動団体 [主な活動地域] | 中間支援主体 [主な活動地域] |
|---|---|
| エコ・グリーンツーリズム水の里しらやま [福井県丹南地域(越前市、鯖江市、越前町、南越前町)] | 合同会社ローカルSDクリエーション [福井県全域] |
| 芋井地区住民自治協議会 [長野県長野市芋井地区] | 認定特定非営利活動法人長野県NPOセンター [長野県全域] |
| 半田市地域循環共生圏推進協議会 [愛知県半田市及びその周辺地域] | 半田市 [愛知県半田市] |
1日目・中間共有会
1日目の中間共有会では、3地域が地域循環共生圏づくりを目指してこれまでに取り組んできた活動やプロジェクト、そして課題となっていることや、今後の展開予定などについてそれぞれ発表していただきました。
3地域の取組発表の後には、本事業の中部の地方事務局である中部地方環境事務所が、地域づくりと地域交通をテーマに情報提供を行いました。3地域は、拠点駅からの二次交通不足や、路線バスの廃止、公共交通の利用促進の必要性など、交通という共通した地域課題を擁していました。そのため、今回の会合で「地域交通」について情報提供を行ったという背景があります。
環境省のグリスロや低炭素モビリティの話題にとどまらず、他省庁関連も含めた交通問題、対応策やその事例等々について触れた資料を作成し提供してくださった中部地方環境事務所の担当者のお話に3地域の皆さんはメモをとりつつ真剣に耳を傾けていました。
地域課題の典型的な例ともいえる交通問題に対し、今やハード・ソフトのみでなく、システム・アプリ・コミュニティ等々による様々な対応策や事例があることなどが紹介され、自分たちの地域で本当に必要な、或いは、可能な対応策とは何であるかを地域全体で考える必要があること、それは地域循環共生圏づくりにもつながる取組の方法でもあることを概説いただきました。


中間共有会の後半では、2ラウンド/2テーマのグループ・ディスカッションを実施しました。ラウンド1は地域別グループによる「(なりたい地域の未来像ではなく)なりたくない地域の未来予想図とその回避宣言を考える」、ラウンド2は地域混合グループによる「私たちの活動、或いは地域循環共生圏事業が地域にもたらすものとは?」をテーマにディスカッションを行いました。
このディスカッションを通して、3地域6団体による取組が各活動地域にどのような意義や意味、貢献性をもつか改めて認識していただき、モチベーションも新たに引き続き、本事業に取り組んでいただけるものと期待をしています!


2日目・視察エクスカーション
2日目は視察エクスカーションを実施しました。午前中は、今回のホストである半田市地域循環共生圏協議会の取組の拠点施設である《ビオクラシックス半田》《にじまち半田農場》を見学しました。《ビオクラシックス》で食品残渣を資源/エネルギーに転換する仕組みを学びながら、その工場施設を見学させていただき、《ビオクラシックス》で生まれたエネルギーが活用されている《にじまち》のミニトマト生産の現場も見学させていただきました。
次に《半田市赤レンガ建物》へ移動し、半田市の地域概要や伝統を今に引き継ぐ市内の発酵食品産業や企業、連携する農家等が展開している資源循環の新しい取組についての半田市観光協会さんによる概説を聴講しました。
そして、その後にいただいた昼食は、この日の視察エクスカーション全体を振り返ることのできるメニューになっていました。半田の資源循環の取組に参画・協力している農家さんのお米や牛肉が食材となっており、大変美味なうえに学びの多いランチを堪能して、本年度の中間共有会は終了しました。

《ビオクラシックス半田》を視察

美味ミニトマト「ミラトマト」が鈴なりの《にじまち半田農場》も見学

《半田市赤レンガ建物》で、半田市観光協会さんによる市内の様々な取組を聴講してからランチへ

昼食は《ビオクラシックス半田》のバイオ肥料で育ったお米と、地域の食品残渣(酒粕、たまり粕)を餌に育てられた知多牛が食材のメニューでした

タグ
月別アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月